これまで、暮らしや福祉に関わる仕事をいくつかご紹介してきました。
でも、世の中にはまだまだ「そんな働き方があるの?」と驚くような職業がたくさんあります。
働くことのカタチが多様化するいま、
“どこで働くか” “何を軸に選ぶか”によって、人生の選択肢も大きく変わっていく時代。
今回は、これまでと少し視点を変えて、
【地域おこし協力隊という意外な仕事】に注目してみたいと思います。
「地方移住って憧れるけど、仕事はどうするの?」
そんな声に応えてくれるのが“地域おこし協力隊”という制度です。
移住・仕事・地域貢献がセットになった、新しい生き方の一歩として、今注目されています。
今回はその制度の内容から、向いている人、収入や暮らしのリアルまでをわかりやすくご紹介していきます。
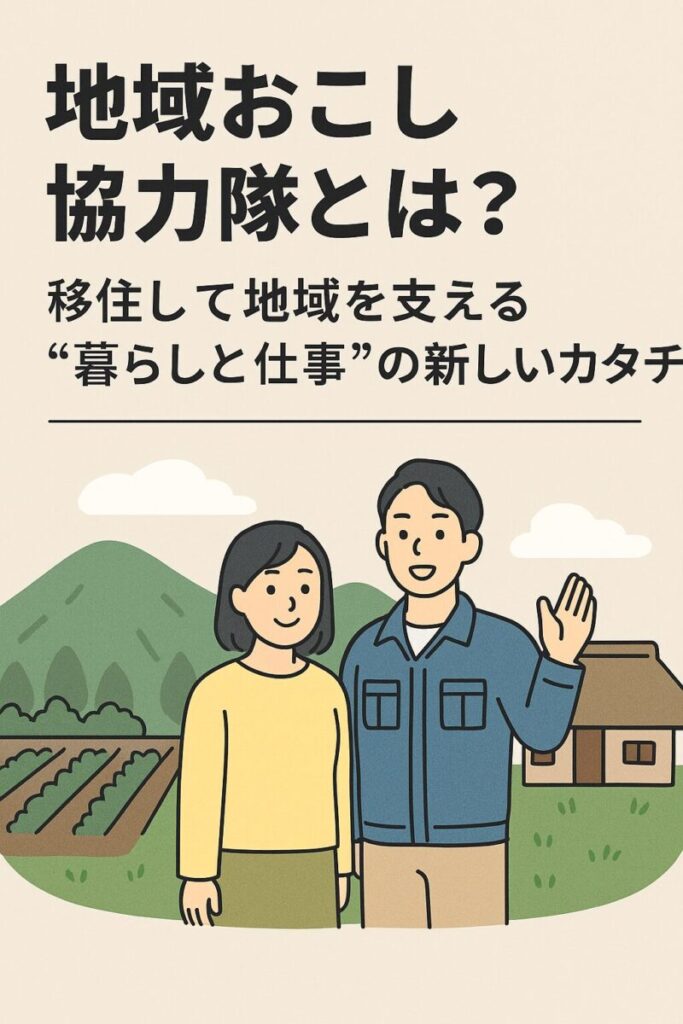
⛰️地域おこし協力隊とは?どんな制度なのか
地域おこし協力隊は、過疎化や高齢化が進む地域の活性化を目的に、2009年に総務省が創設した制度です。
特に人口減少・担い手不足が深刻な農山村・離島地域では、外部の力が求められていました。
都市部に住む人の「地方移住への関心」と、地域の「人手不足」という課題を結びつけるために生まれたのがこの制度です。
単なる労働力ではなく、地域に“新しい風”をもたらす人材としての期待も込められています。
要点をまとめるとこんな感じになります。↓
- 総務省によって創設された地方創生のための制度
- 都市部から地方へ移住し、地域活動を行うことが前提
- 活動期間は概ね1年〜3年、自治体との契約で報酬あり
- 近年は20代~40代を中心に注目されている
⛰️地域おこし協力隊の主な活動内容
地域おこし協力隊の活動内容は、地域によって実に多様です。以下は一例です。
- 観光PR:地域の魅力をSNSやイベントで発信
- 農業支援:高齢化する農家を手伝ったり、収穫体験を企画
- 地域資源活用:古民家・伝統工芸・自然環境を活かした事業づくり
- 特産品の開発:地元食材を使った新商品づくりや販路開拓
- 空き家再生:リノベーションしてカフェやゲストハウスに活用
- 子育て支援・高齢者サポート:保育、見守り、地域行事の企画など
また、最近では以下のような制度も増えています
- 起業支援型のプログラム
- 副業・兼業OKの自治体もあり
👉 自治体ごとにテーマが異なるため、「地域で何が求められているか」を自分で考え、能動的に動ける人に向いている制度です。テーマはお住まいの自治体のホームページにて確認ください。
💼どんな人に向いてるか?
地域おこし協力隊は、スキルよりも「価値観」や「暮らしへの意欲」が重視されます。
こんな人には特に向いていると言えるでしょう。
地方暮らしに興味がある人
→ 自然の中でのんびり暮らしたい方に最適
地域に貢献したいという思いがある人
→ 人の役に立ちたい・感謝される仕事がしたい方
起業や新しいキャリアに挑戦したい人
→ 任期中の準備期間を活かして独立も可能
人間関係を大事にしたい人
→ 地域密着の活動なので、信頼関係づくりが大切です
👉 自分の価値観とマッチしていれば、スキルや経験がなくても飛び込める制度です。
💰収入や生活面のリアル
「地方に移住して暮らす」と聞くと、収入面に不安を感じる方も多いはずです。
地域おこし協力隊では、生活を支えるための報酬やサポート制度が整備されていますが、都市部の生活とはやや異なる現実があります。
💰収入の目安とサポート内容
月額報酬:約15万円〜25万円(自治体によって異なる)
→ 公務員ではなく「業務委託」または「会計年度任用職員」として契約されることが多いです。
住居費補助あり:空き家を無償または低額で借りられるケースも多い
→ リフォーム費用を自治体が支援する例もあります。
活動費の支給:移動費・備品・企画費などに年間100万円〜200万円程度の支援があることも
副業OKの自治体も増加中
→ 自由度の高い働き方を選べる自治体も多くなっています
🛠 地域で“自分らしく働く”ために学べる講座も
「地域おこし協力隊として活動しながら、自分の得意なことを活かして起業したい」
「任期後の働き方について、今から準備をしておきたい」
そんな想いを持つ方に向けて、起業やビジネススキルを学べる講座もあります。
たとえば、総務省が運営する「JOIN(一般社団法人 地域力創造アドバイザー)」では、
地域おこし協力隊向けに以下のようなサポートを実施しています:
- 起業の基本が学べる座学講座
- 現地ワークショップや実践型プログラム
- ビジネスプランに関する個別相談など
▶ 詳細はこちら:https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/11095.html (JOIN(地域おこし協力隊の全国受け入れ組織)
こうした講座は、参加費が無料だったり、自治体ごとに補助制度があることも。
「興味はあるけど不安もある…」という方こそ、気軽に情報収集してみるのがおすすめです。
📚 紹介書籍とおすすめポイント
地域おこし協力隊について「もっと深く知りたい」「実際に参加した人の話を読んでみたい」と感じた方もいるかもしれません。
制度の仕組みだけでなく、
・どんな人が参加しているのか
・現場でどんな悩みややりがいがあるのか
・実際にその後どうキャリアを築いているのか
…といったリアルな情報を知るには、書籍を手に取ってみるのもひとつの方法です。
今回は、これから地域おこし協力隊を考えている方にぴったりの本を2冊ご紹介します。👇
『地域おこし協力隊 日本を元気にする60人の挑戦』全国各地で活躍する60人の実例を紹介!👉 活動スタイルや制度の具体像がリアルにわかる一冊
📘 活動スタイルや制度の具体像がリアルにわかる一冊
地域おこし協力隊の実例60人を紹介した書籍。
どんな人が、どの地域で、どんな挑戦をしているのかがリアルにわかります。
※地域おこし協力隊の“中の人”のリアルな声を知りたい方におすすめです。
『「地域おこし協力隊」は何をおこしているのか?移住の理想と現実』理想と現実、そのギャップに向き合う一冊
🏡 移住と制度のリアルを知るならこの一冊
地域おこし協力隊の理想と現実、そのギャップに向き合う
若者の視点から語られた、リアルな移住の課題と発見。
※「理想と現実」のリアルな声を知りたい方、これから移住を考える方に最適です。
🏠生活のリアル
都会に比べて生活費は抑えやすく、自然に囲まれた暮らしができる
一方で買い物・医療・インフラ面の不便さは覚悟が必要
「職場と生活圏が密接」なので、公私の切り替えが難しいと感じる人もいるかもしれませんね。
👉 移住前に現地を訪れて体感することがとても重要です。
ミスマッチを防ぐためにも、事前の情報収集と地域とのコミュニケーションは欠かせません。
始め方と応募の流れについて
🔹STEP①:自治体の募集を探す
自治体のホームページや移住フェアなどでも募集情報が公開されています
「JOIN(移住・交流推進機構)」の公式サイトが最も情報が豊富
→ https://www.iju-join.jp/
🔹STEP②:募集内容を確認する
募集地域の活動内容・条件・報酬などを詳細にチェック
特に「住居支援」「副業の可否」「車の必要性」など、生活面の条件も確認しておきましょう
TEP③:応募書類の提出
履歴書や志望動機書、活動プランの提出が求められることが多いです
書類審査のあと、面接選考が行われます(近年だとオンライン面接の場合もあるようです)
STEP④:採用後に地域へ移住
- 合格後は自治体と契約し、現地での暮らしと活動がスタートします
- 任期開始後は、自治体職員や地域住民との連携を取りながら業務を進めます
👉 地域との相性が大切なので、応募前に現地見学をするのがおすすめです。
自治体によっては「お試し移住制度」や「インターン制度」を設けているところもあります。
制度の課題と今後の可能性
地域おこし協力隊は多くの自治体で導入が進み、地域活性化に一定の成果を上げています。
しかし、制度としてまだ課題もあり、今後の運用や支援のあり方が問われています。
🔹現状の課題
ミスマッチの発生
→ 実際に移住してみたら仕事内容や人間関係が想像と違ったという声も中にはあるようです
任期後の進路が不安定
→ 定住や起業を目指していても、支援が十分でない地域もあります
受け入れ側の体制が不十分なケース
→ 担当者不在やサポート不足で孤立する協力隊員も・・・
🔹今後の可能性と改善の動き
制度の柔軟化:副業OKや「プロ人材型」など多様な働き方が可能に
起業・定住支援の強化:自治体やNPOによるアフターサポートが拡充中
全国的な連携:他地域の協力隊とつながるネットワークも増加
👉 課題があるからこそ、自分に合った地域や制度設計を見極める目が大切です。
そのうえで、制度を“利用する”のではなく、“共に作っていく”視点を持つことで、活動の充実度はぐんと高まります。
💡ふるさと納税
地域の魅力を“味わって”応援しませんか?
地域おこし協力隊の活動地には、まだ知られていない魅力がたくさんあります。
その地域を知る第一歩として、「ふるさと納税」で特産品を取り寄せてみるのもおすすめ。
- 地元の旬の野菜・お米・海産物
- 手作りの加工品やお菓子
- 地域のクラフトビールや伝統工芸品
など、「体験を通じて地域とつながる贈り物が見つかります」
①【地域の暮らしを感じる定番セット
季節の恵みを詰め込んだ旬の野菜詰め合わせ
👉 北海道や美瑛町の味覚をご自宅で
🍅【地域の暮らしを感じる定番セット】
季節の恵みを詰め込んだ旬の野菜詰め合わせ
👉 北海道や美瑛町の味覚をご自宅で
「どの野菜も甘みがあってびっくり。届いた日が、ちょっとしたごちそう日になります。」
②【加工食品・保存食】
“地方の味”を気軽に体験
👉高知県須崎市の鰹のたたきセット
②【加工食品・保存食】
“地方の味”を気軽に体験
👉 高知県須崎市の鰹のたたきセット
「藁の香ばしさが、食卓にちょっとした旅気分を届けてくれます。冷凍とは思えない美味しさです。」
③“暮らしを彩る”ローカルアイテム
岐阜県関市の職人技が光る包丁セット日々の料理が楽しくなる、一生モノの一本
👉 岐阜県関市の職人技が光る包丁セット
③“暮らしを彩る”ローカルアイテム
岐阜県関市の職人技が光る包丁セットは、日々の料理が楽しくなる、一生モノの一本
👉 岐阜県関市の職人技が光る包丁セット
「料理好きなら一度は使ってみたい“切る感動”。日々の調理が楽しみになる一本です。」
「地域の風土」が香る一杯を
長野県伊那市のクラフトビール6本セット
👉 ちょっとした贅沢に。自分へのご褒美としてビール6本セット
④「地域の風土」が香る一杯を
長野県伊那市のクラフトビール6本セット🍺
👉 ちょっとした贅沢に。自分へのご褒美としても
「地域の個性が詰まった一杯。週末のご褒美タイムにぴったりなセットです。」
👆直接的ではなく間接的に地域おこしに協力したい人へふるさと納税は最適と言えます👆
- 「地域の想いが詰まった、ひと品です。」
- 「暮らしに、ふるさとの温もりを。」
- 「選ぶことで、地域を応援できます。」
- 「ちょっといいもの、ちょっといい時間。」
- 「届けたいのは、“味”と“物語”です。」
まとめ:自分らしく、地域とつながる暮らし
地域おこし協力隊は、ただの「移住支援制度」ではなく、
“その土地で生きる”という選択を応援してくれる仕組みです。
都会の忙しさから少し離れて、自然のある暮らしの中で、
人と出会い、地域と関わりながら、少しずつ自分のペースで働くことができます。
- 特別な資格がなくてもはじめられる
- 地域に必要とされながら、暮らしが形になっていく
- 終了後の進路にもつながる“土台”を作れる
不安があるのは当たり前。だからこそ、情報を集めて、現地の空気を感じてみてください。
「ここで暮らしてみたい」と思える場所がきっと見つかるはずです。
あなたの一歩が、地域に新しい風を運びますようにこれからの手助けになれば幸いです。
💬「こんな仕事も知りたい!」「気になる職業がある!」などあれば、ぜひコメントやSNSで教えてくださいね。
✉️「これって仕事になるの?」と気になる職業があれば、お気軽にお知らせください。
あなたの声が、次の記事につながります。次回の記事の参考にさせていただきます♪




コメント