家の中で「ここ、ちょっと危ないかも」と感じたことはありませんか?
特に高齢の家族がいると、ほんの少しの段差や滑りやすい床が不安材料になることも。
そんな“住まいの不安を解消し、安心して暮らせる環境を整えるために活躍しているのが、福祉住環境コーディネーターという存在です。
介護のことはわかるけど、住まいのことまでは…」
そんなギャップを埋める、まさに福祉×建築の専門家。
今回は、この知られざる仕事の魅力と可能性についてご紹介します。
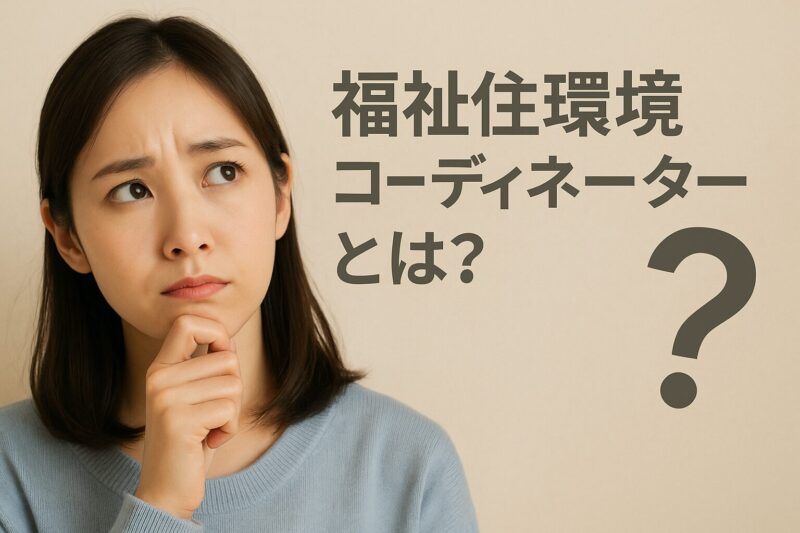
- 福祉住環境コーディネーターの仕事が何かわかる
- 資格の取得方法がわかる
- 高齢者と密着な役割がわかる
福祉住環境コーディネーターとは?
日本は現在、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進む「超高齢社会」を迎えています。65歳以上の高齢者はすでに人口の約3割を占めており、その数は今後も増加傾向にあります。こうした中で、病院や施設ではなく「住み慣れた自宅で暮らしたい」という希望を持つ高齢者が多く、在宅介護のニーズが急速に高まっています。
・しかし、現実はどうでしょうか。
・ちょっした段差でつまずきやすい
・日本家屋では構造上で車いすでは通れない廊下やドア幅が多く見受けられています。
・また、浴室やトイレでの事故
など、家庭内の環境が生活の妨げになることも少なくありません。
これらを解消するために誕生したのが、住まいと福祉の両面を考慮できる専門家=福祉住環境コーディネーターです。老老介護も多い中で暮らしの質(QOL)を高め、介護する側・される側の負担を減らすための「環境整備の視点」が、ますます求められています。
仕事内容と活躍の場
住宅のバリアフリー提案や介護リフォーム相談
福祉住環境コーディネーターの代表的な業務の一つが、住宅のバリアフリー化に関する提案や介護リフォームの相談対応です。例えば・・・
*「浴室に手すりをつけたい」
*「車いすでも玄関に出入りしやすくしたい」
*「将来に備えて段差をなくしたい」
といった相談を受け、利用者の身体状況・家族構成・住宅構造・介護方針などを総合的に考慮したプランを提案します。単に設備を追加するだけでなく、介護者の動線や経済的負担まで視野に入れて調整できるのが、福祉住環境コーディネーターならではの視点です。
ケアマネ・建築士・福祉用具専門相談員などとの連携
この仕事の大きな特徴は、「ひとりで完結しない」という点にあります。
福祉住環境の改善には、さまざまな専門職との連携が欠かせません。他職種とのチームでの連携する重要な役割を担っています。次に他職種が何を専門としているかみていきましょう。
ケアマネジャー(介護支援専門員)
→介護保険を利用している利用者に対して利用者の介護サービス計画(ケアプラン)を把握し、必要な改修を相談
建築士・工務店の担当者
→提案内容を実現するための設計・施工面でのアドバイスや実作業
福祉用具専門相談員
→手すり、歩行器、スロープなどの適切な選定・配置をサポート
このように、「人を中心にしたチームづくり」ができる人材として、コーディネーターの存在は高く評価されています。
働ける場所(自治体/工務店/福祉用具会社/独立開業)
福祉住環境コーディネーターはさまざまな場所で活躍しています。以下に、代表的な就業先を分けてご紹介します。
【1. 自治体(福祉課・住宅課など)】
地域住民の住宅改修や助成制度の相談窓口として、福祉や住まいの専門知識を活かして対応。高齢者向け住宅支援や地域包括支援センターとの連携も多く、公的支援の現場で活躍できます。
【2. 工務店・リフォーム会社】
バリアフリーリフォームの相談役として、営業や設計スタッフとチームで動きます。高齢者の住まいに特化した提案力が求められ、建築の現場で福祉視点を加える存在となります。
【3. 福祉用具会社・介護用品店】
手すりや昇降機、歩行補助具などを扱う福祉用具販売の現場では、住宅構造を踏まえた配置や選定のアドバイスができるスタッフとして重宝されます。利用者宅に同行し、提案や設置支援を行うことも。
【4. 独立・フリーランス】
近年では、福祉住環境コーディネーターとして個人で起業するケースも増加しています。ケアマネや工務店からの依頼を受けてアドバイザーとして活動したり、自身の経験を活かしてセミナー講師やコンサル業務を行うことも可能です。
このように、活躍の場は建築・福祉・行政と多岐にわたっており、自分の強みや経験に応じて働き方を選べる柔軟さもこの資格の魅力です。
福祉住環境コーディネーターの収入事情
福祉住環境コーディネーターの収入面については、「職場の種類」「資格の活かし方」「他の資格との組み合わせ」によって大きく差が出るのが特徴です。以下に、具体的な働き方別にまとめてご説明していきます。
▶ 工務店・リフォーム会社などの社員として働く場合
多くは営業職や設計職と兼務し、月収20万~30万円台が一般的です。
ただし、福祉住環境コーディネーターの資格を持っていると、公共助成制度の申請対応や福祉リフォーム案件を任されやすくなるため、成果によっては歩合や役職手当がつくこともあります。
▶ 福祉用具会社・福祉施設の職員として働く場合
介護職や相談員の延長線上として働くことが多く、収入水準は年収300~400万円前後。
ただし、住環境整備の知識があることで職域が広がり、資格手当(月5,000~10,000円)を支給している事業所もあります。
▶ 自治体・地域包括支援センターなど公的機関勤務
正規職員の場合、地方公務員の給与規定に準じて年収400万円台〜600万円程度。
業務の中に住環境の相談対応が含まれる形で、専門知識を活かす場面が多くあります。
▶ フリーランス・副業として活かす場合
福祉住環境コーディネーターの資格だけで独立開業は全国的にみても少なめですが
- 建築士や介護福祉士、ケアマネ資格と組み合わせる
- リフォーム会社やケアマネへのコンサル契約
- 住宅改修の助成金申請サポート(行政書士との連携)
などで活動すれば、1件数万円〜十数万円の報酬も見込めます。
経験・実績・営業力次第では年収600万円以上を目指すことも可能と言われています。
向いている人はどんな人?・必要なスキルはある?
「誰かの暮らしに寄り添いたい」気持ち
福祉住環境コーディネーターに最も大切なのは、「技術」よりもまずその人らしい生活を支えたいという思いです。福祉住環境コーディネーターに限らず技術は後からついてくるものが多いものです。
この仕事では、単に手すりを付ける・段差をなくすといった作業以上に、
「この人はどんな暮らしをしたいのか?」
「家族とどんな時間を過ごしたいのか?」
を考える力が求められます。そのため、「目の前の人のために役立ちたい」と感じる方や、介護・福祉の経験を通じて環境の重要性に気づいた方には特に向いています。
「暮らしの課題を“設備”で解決する視点」が身につくことで、これまでとは違うかたちで誰かを支えるやりがいを感じられるでしょう。
コミュニケーション力・提案力が求められる
福祉住環境コーディネーターは「人の話を聞く力」と「相手に伝える力」の両方が求められる仕事です。まず、住まいの相談に来る人の多くは、漠然とした不安や要望を抱えています。例えば・・・
「母が最近よく転ぶようになって…」
「お風呂に入るのがつらくなってきた」
といった相談を、一つ一つ丁寧に聞き取る「ヒアリング力」が重要です。そして、それに対して「具体的にどう改善できるか」を専門用語を使わずに、誰にでもわかる言葉で提案する力も欠かせません。さらに、ケアマネジャーや建築士など他の専門職と協力する場面も多く、信頼関係を築くコミュニケーション力が仕事の質を左右します。
まとめると向いている人はこんな人
- 相手の立場に立って考えるのが得意な人
- 困っている人を見ると放っておけないタイプ
- 聞き上手・話し上手のどちらも目指したい人
- 現場経験を活かしてステップアップしたい人
資格の取り方とキャリアパス
受験資格・難易度・合格率はどんな感じになっているでしょう。
福祉住環境コーディネーターの資格は、東京商工会議所が主催する公的な民間資格です。
1級・2級・3級の3段階がありますが、2級・3級は誰でも受験可能で、年齢・学歴・実務経験などの条件は一切ありません。
難易度と出題傾向(2級・3級)
- 3級:初学者向け。福祉や住宅についての基礎的な理解があれば合格可能。
- 2級:やや実務寄りの内容で、介護保険制度、建築基準法、リフォーム事例など幅広い知識が問われます。
▶ 合格率の目安(年度により変動あり):
- 3級:40〜50%前後
- 2級:30〜40%前後
独学でも合格は可能ですが、テキストや過去問を活用したり、通信講座を利用する人も多いです。試験は年に数回(主に6月・11月)実施され、在宅受験も可能な回があるため、社会人や主婦でもチャレンジしやすい点が人気の理由です。
福祉職や建築職との相乗効果福祉住環境コーディネーターの資格は、それ単体で「就職に直結する」というよりも、他の専門資格と組み合わせることで強みが増す資格です。
福祉系職種との相乗効果
介護福祉士やケアマネジャー
→ 利用者の生活背景を深く理解しているからこそ、「暮らしに合った住まいの改善提案」ができるように。
→ 介護保険制度に詳しい人ほど、住宅改修との連携に強みになります。
建築・住宅系職種との相乗効果
建築士・リフォーム営業・インテリアコーディネーターなど
→ デザイン性や施工性に加えて、「福祉的な視点」での安全性や使いやすさを提案できるように。
→ 介護リフォームに強い工務店として差別化につながります。
このように、自分の専門分野に「住まいの視点」をプラスするだけで、キャリアの幅が一気に広がるのがこの資格の魅力の一つです。
この仕事のやりがいと将来性
利用者の「ありがとう」がやりがいに
福祉住環境コーディネーターの仕事は、生活の「安心」と「自立」を支えることに直結しています。
「段差をなくしたことで母が安心して歩けるようになった」
「お風呂に手すりを付けたら、介助がずっと楽になった」
といった変化は、生活する人の負担を減らすだけでなく、心の余裕や家族関係の改善にもつながることがあります。
その結果、「あなたのおかげで暮らしが変わった」「今の家がもっと好きになった」という感謝の言葉を直接もらえる機会も多く、目に見える形で人の役に立てる実感を得やすい仕事です。
特に介護職など現場経験がある方にとっては、これまでと違った角度で人を支える新たなやりがいを感じられるかもしれません。
在宅医療・地域包括ケア時代に求められる存在
日本では今後ますます、「できる限り自宅で暮らし続ける」ことが前提の社会になります。
医療・介護サービスを地域全体で支える「地域包括ケアシステム」が進められる中で、自宅での生活を支える住環境整備の重要性は高まる一方です。また、在宅医療や訪問看護・介護を受ける人の増加に伴い、住宅側の配慮や設備の整備が不可欠になっています。例えば・・・
- ベッドの位置と動線の確保
- 車いすが通れる廊下幅の確保
- 酸素や吸引器の配置を想定した間取りの工夫
といった調整は、医療・介護の現場と住まいをつなぐ視点を持つ人材がいなければ成り立ちません。
福祉住環境コーディネーターは、まさにこうしたニーズに応える「これからの地域に必要とされる職業」として、今後さらに注目を集めていくでしょう。
「今すぐ始めたい!」という方へ、まずはこの教材やアイテムから始めてみませんか?
▼【独学OK】最短で合格したい人へ!公式テキストはこちら
→ 独学にも対応!信頼の一冊はこちら👇
▼【現場で活かせる】プロの提案力が身につく事例集はこちら
→ 現場で活用できる実例をチェック👇
「これ一冊で基礎から合格まで」「リフォーム提案の引き出しに」
住まいから支える、もう一つの介護のかたち
福祉住環境コーディネーターは、
「医療や介護の支援は届いていても、住まいの環境が整っていない」
そんな 見落とされがちな暮らしの課題を解決する存在です。
- 自宅での生活をあきらめないために
- 利用者にも家族にも優しい住まいをつくるために
- 多職種と連携しながら地域を支える一員として
この資格は、単なるスキルではなく、これからの社会を支える新しい視点を与えてくれます。
最初の一歩を踏み出すには?
この記事を読んで少しでも「自分にもできるかも」と感じた方は、まずは2級・3級の取得を目指すことから始めてみましょう。
在宅受験や独学も可能ですが、効率よく学びたい方には通信講座や公式テキスト・問題集の活用がおすすめです。
【公式テキスト】福祉住環境コーディネーター検定試験3級(東京商工会議所)
→ 基本から応用まで網羅した信頼の一冊



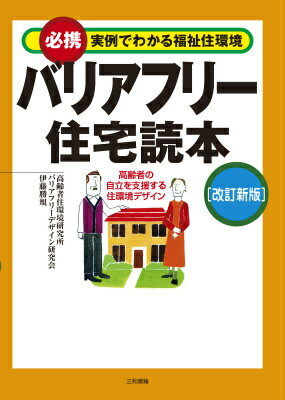

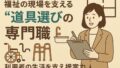
コメント